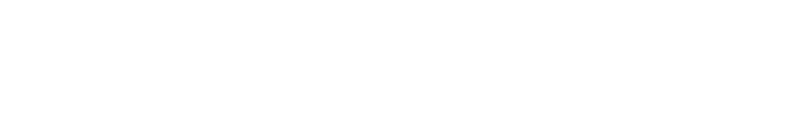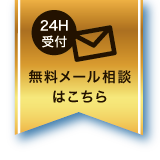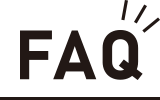

自己破産すると仕事にどんな影響が出るの?
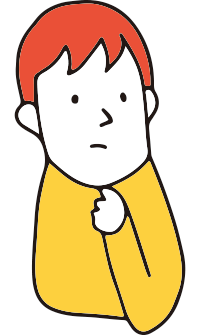 どうやっても返せないほどの借金があるならさっさと自己破産してまた一からやり直せばいいと思うのですが、自己破産すると仕事に悪影響が及ぶと聞きました。それは本当なのでしょうか?
どうやっても返せないほどの借金があるならさっさと自己破産してまた一からやり直せばいいと思うのですが、自己破産すると仕事に悪影響が及ぶと聞きました。それは本当なのでしょうか?先日借金で首が回らなくなっている友人からお金を貸して欲しいと言われ、私も彼ほどではないですが消費者金融などからお金を借りているので余裕はないと断りました。
そのときに友人に実際のところ現状どうなっているか聞くと、すでにいろいろなところに相談に行ったのだけど、人によって提案される解決策も違い、自己破産しようとしたら仕事にも影響するから他の方法を選択した方がいいとアドバイスされて、どうしていいか困惑しているとのことでした。
私はサラリーマンをしていますが、自己破産して会社をクビになるようなことはあるのでしょうか?
例えば、サラリーマンでなく手に職がある人が自己破産したら、仕事で使う道具を取り上げられて仕事ができなくなるのでしょうか?友人はそこも心配していました。
自己破産により大きな影響を受けるような特定の仕事があれば、それについても教えて欲しいです。あと、自己破産すると家や車などの財産は没収されると思うのですが、給料やボーナスも没収されてしまうのでしょうか?
![]()

サラリーマンなら基本的には仕事に影響しません
まず、サラリーマンであれば基本的に自己破産しても仕事に悪影響が及ぶことはありません。これまでと同じように働くことができますし、転職して新しい仕事に就くことも問題なくできます。
そもそも、自己破産したら仕事ができなくなるという法律はなく、自己破産は人生をやり直すために全ての国民が利用できる制度です。
自己破産しても、そのことを会社に知られることもないですし、たとえ会社内に知られたとしても、自己破産が正当な解雇事由になることは原則としてありません。もし解雇されたら不当解雇に該当するケースがほとんどでしょう。
自己破産しても、仕事に必要な道具を処分されることもありません。仕事に使う道具まで奪われてしまうと、社会復帰がままならなくなってしまうので、そのような心配は不要です。もっとも、仕事に関係するものであれば全て残せるわけではありません。処分を免れるのは、原則として業務に欠かせない道具や資産価値のない物などです。
手元になくても業務に差し支えがない余分な財産や事業設備については、一定の資産価値がある場合には、換価の対象になってしまいます。
また、自己破産しても、これまでに取得した資格が剥奪されるということもありません。資格を活用して働くことも可能です。ただし、一部の職業や資格では制限がかかることがありますので、その場合は注意が必要です。
自己破産によって影響を受ける資格や職業は、具体的に定められています。それは、「士業」「金融関連業」「その他の職業」「公務員」「団体企業の役員」などです。
士業に関しては、弁護士、税理士、司法書士、弁理士、公認会計士、不動産鑑定士などが該当します。
金融関連業は、貸金業者、質屋・古物商、生命保険募集人といった他人の財産を扱う職業が対象となっています。
その他職業としては、旅行業務取扱管理者、警備員、建設業、風俗業、廃棄物処理業、調教師や騎手などが該当します。
公務員に関しては、都道府県公安委員会、公正取引委員会、教育委員会、公証人、人事院などの委員や委員長などが対象です。
団体企業の役員に関しては、商工会議所、金融商品取引業、信用金庫、日本銀行などの役員の場合は自己破産によって職務を継続できなくなってしまいます。
このように、自己破産をして制限を受ける資格や職業はありますが、ずっと制限が続くわけではありません。破産手続きの開始から復権までの期間は早くて約3カ月程度となっていて、一般的には半年程度が目安となります。
サラリーマンが自己破産すると、給料やボーナスがどうなるか気になる方が多いと思います。
すでに受け取っている給料やボーナス関しては、現金や預貯金として取り扱われ、生活に最低限必要な金額は手元に残すことができます。ただし、それを超える分は回収される場合があります。
具体的には、手元にある現金が99万円以下の場合は、自由財産として破産者が保有できると破産法で決まっているため、それを超える部分は回収の対象になります。
但し、手元にある現金が33万円を超える場合は、破産管財事件として扱われますので、その点は注意が必要です。
また、将来的に退職金を受け取ることが見込まれる場合においては、破産申立時点での退職金見込額を算出する必要があり、その8分の1が財産と見なされて回収される可能性もあるので注意が必要です。
そもそも、自己破産したら仕事ができなくなるという法律はなく、自己破産は人生をやり直すために全ての国民が利用できる制度です。
自己破産しても、そのことを会社に知られることもないですし、たとえ会社内に知られたとしても、自己破産が正当な解雇事由になることは原則としてありません。もし解雇されたら不当解雇に該当するケースがほとんどでしょう。
自己破産しても、仕事に必要な道具を処分されることもありません。仕事に使う道具まで奪われてしまうと、社会復帰がままならなくなってしまうので、そのような心配は不要です。もっとも、仕事に関係するものであれば全て残せるわけではありません。処分を免れるのは、原則として業務に欠かせない道具や資産価値のない物などです。
手元になくても業務に差し支えがない余分な財産や事業設備については、一定の資産価値がある場合には、換価の対象になってしまいます。
また、自己破産しても、これまでに取得した資格が剥奪されるということもありません。資格を活用して働くことも可能です。ただし、一部の職業や資格では制限がかかることがありますので、その場合は注意が必要です。
自己破産によって影響を受ける資格や職業は、具体的に定められています。それは、「士業」「金融関連業」「その他の職業」「公務員」「団体企業の役員」などです。
士業に関しては、弁護士、税理士、司法書士、弁理士、公認会計士、不動産鑑定士などが該当します。
金融関連業は、貸金業者、質屋・古物商、生命保険募集人といった他人の財産を扱う職業が対象となっています。
その他職業としては、旅行業務取扱管理者、警備員、建設業、風俗業、廃棄物処理業、調教師や騎手などが該当します。
公務員に関しては、都道府県公安委員会、公正取引委員会、教育委員会、公証人、人事院などの委員や委員長などが対象です。
団体企業の役員に関しては、商工会議所、金融商品取引業、信用金庫、日本銀行などの役員の場合は自己破産によって職務を継続できなくなってしまいます。
このように、自己破産をして制限を受ける資格や職業はありますが、ずっと制限が続くわけではありません。破産手続きの開始から復権までの期間は早くて約3カ月程度となっていて、一般的には半年程度が目安となります。
サラリーマンが自己破産すると、給料やボーナスがどうなるか気になる方が多いと思います。
すでに受け取っている給料やボーナス関しては、現金や預貯金として取り扱われ、生活に最低限必要な金額は手元に残すことができます。ただし、それを超える分は回収される場合があります。
具体的には、手元にある現金が99万円以下の場合は、自由財産として破産者が保有できると破産法で決まっているため、それを超える部分は回収の対象になります。
但し、手元にある現金が33万円を超える場合は、破産管財事件として扱われますので、その点は注意が必要です。
また、将来的に退職金を受け取ることが見込まれる場合においては、破産申立時点での退職金見込額を算出する必要があり、その8分の1が財産と見なされて回収される可能性もあるので注意が必要です。
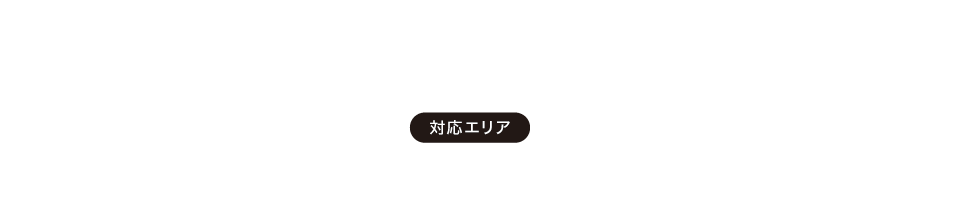
Copyright(C) 横浜SIA法律事務所 All Right Reserved.