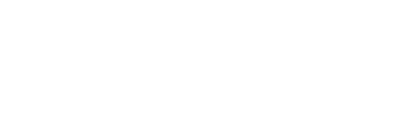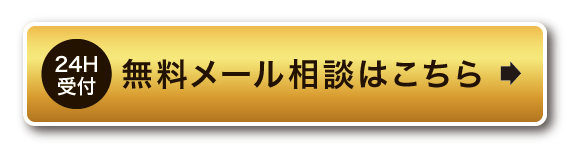個人再生はサラリーマンでもできますか?
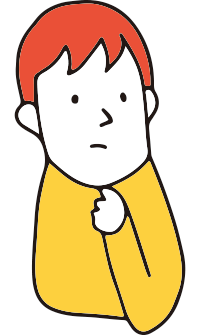 横浜市内でサラリーマンをしている者です。妻と子供が一人いて、結婚して2年後にはマイホームを建てて、結婚後10年間は特に問題なく普通の暮らしをしてきました。
横浜市内でサラリーマンをしている者です。妻と子供が一人いて、結婚して2年後にはマイホームを建てて、結婚後10年間は特に問題なく普通の暮らしをしてきました。しかし、新型コロナウイルス感染症が流行して勤めていた会社の業績が悪化し、転職を余儀なくされて収入が以前よりも少なくなりました。
不足分を補うために消費者金融のカードローンやクレジットカードのキャッシングなどにも手を出してしまい、今年に入ってからは返済が苦しくなり、債務整理を考えるようになりました。妻も子育てをしながらパートに出て働いていますが、借金は一向に減っていきません。
このままでは借金の返済を滞納してしまうので、自己破産してゼロからスタートしようとしましたが、ある人から個人再生という家を残して借金を大幅に減らせる方法があると聞きました。
個人再生は普通のサラリーマンでもできるのでしょうか?できるなら、個人再生するための条件などを分かりやすく教えてください。


サラリーマンでも個人再生できます
個人再生は債務整理の一種で、家や車などの財産を残しながら借金を大幅に減額できるのが大きな特徴でありメリットです。
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、給与所得者等再生は、安定収入のある会社員などが対象となっています。したがって、サラリーマンでも個人再生はできます。
ちなみに、個人事業主は給与所得者再生を使用することができません。小規模個人再生は、主に個人事業者が対象ですが、サラリーマンでも利用可能となっています。
いずれの場合も、個人再生を利用するには安定収入を得ていなくてはいけないという開始条件があります。
個人再生が認められれば、借金の大幅減額ができますが、それでも毎月一定額を3〜5年の間返済していく必要があります。返済を続けるためには、継続した安定収入があることが必須条件です。
毎月一定の金額を継続的に得られる環境に置かれているサラリーマンなら、個人再生が認められやすいです。収入が安定しないパートやアルバイトでは、安定収入を得ることが難しいと判断される可能性が高いです。
しかし、パートやアルバイト、個人事業主、年金受給者などでも、場合によっては安定収入があると認められることもあります。
安定収入の要件は、返済を続けていけるかという観点から総合的に判断されます。そのため、必ずしもサラリーマンなどの正社員でなければいけないというわけではありません。
パートやアルバイトでも、正社員と同様に雇用契約であれば基本的に個人再生が認められます。ただし、短期間でのパートやアルバイトを繰り返しているようなケースにおいては、継続的な収入の見込みがないと判断される可能性が高いです。
安定した収入があっても、住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円以上になるような場合は、小規模個人再生、給与所得者再生いずれの対象にもなりません。債務総額が5,000万円を超えている場合は、通常の一般民事再生手続の対象となります。
個人再生を実行に移すためには、裁判所へ申し立てをして審査をパスしなくてはいけません。再生計画案の内容を裁判所が審査し、債権者の異議も出なければ認可決定が出ることになります。
再生計画案は、実際に実行可能なものでなければ裁判所に認められません。再生計画案の実行可能性は、主に家計収支表に照らして判断されることになります。
例えば、家計の余剰が5万円しかないのに、月額の返済が7万円の再生計画案を提出すれば、当然ですが実行可能性がないと判断されます。
また、個人再生では種類に応じて最低弁済額の基準が設けられています。再生計画案は、最低弁済額を上回る金額で作成されていなければなりません。
給与所得者再生の場合は、「債務総額を金額に応じて圧縮した後の額」「財産の総額」「可処分所得の2年分」の3つを比較して最も高い額が最低弁済額となります。
可処分所得については、給与明細や課税証明、源泉徴収票などをもとに一定の計算式で求められます。給与所得者再生の場合、可処分所得が最低弁済額となることが多く、返済額が高くなりがちです。
個人再生の申立てをした後も、裁判所の指示に適切に従わないと手続きを進めることができなくなってしまいます。
個人再生の申立書類が裁判所に届くと、裁判所ではまず書類に不備がないか確認します。不備があれば補正の可能性の有無によって、補正の可能性があれば補正の指示があります。
明らかに補正の可能性がなければ、申立て不適法ということで却下され、それ以降の手続きはされずに終わります。
補正不可能な不備とは、負債総額が5000万円を超えていたり、手続費用を期限までに納付しなかったり、債務者が個人ではなかったりなどの、そもそも個人再生の条件を満たしていない場合などです。
補正可能な不備とは、単純な誤記や記入漏れ、必要な種類が添付されていなかったりした場合などです。
個人再生の申立てをすると、一般的には1週間程度で裁判所から追完指示がきます。追完の期限は通常2週間とされていますので、その期間中に不備を修正して再提出してください。どうしても間に合わない場合は、期限の延長許可を求めることもできます。
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、給与所得者等再生は、安定収入のある会社員などが対象となっています。したがって、サラリーマンでも個人再生はできます。
ちなみに、個人事業主は給与所得者再生を使用することができません。小規模個人再生は、主に個人事業者が対象ですが、サラリーマンでも利用可能となっています。
いずれの場合も、個人再生を利用するには安定収入を得ていなくてはいけないという開始条件があります。
個人再生が認められれば、借金の大幅減額ができますが、それでも毎月一定額を3〜5年の間返済していく必要があります。返済を続けるためには、継続した安定収入があることが必須条件です。
毎月一定の金額を継続的に得られる環境に置かれているサラリーマンなら、個人再生が認められやすいです。収入が安定しないパートやアルバイトでは、安定収入を得ることが難しいと判断される可能性が高いです。
しかし、パートやアルバイト、個人事業主、年金受給者などでも、場合によっては安定収入があると認められることもあります。
安定収入の要件は、返済を続けていけるかという観点から総合的に判断されます。そのため、必ずしもサラリーマンなどの正社員でなければいけないというわけではありません。
パートやアルバイトでも、正社員と同様に雇用契約であれば基本的に個人再生が認められます。ただし、短期間でのパートやアルバイトを繰り返しているようなケースにおいては、継続的な収入の見込みがないと判断される可能性が高いです。
安定した収入があっても、住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円以上になるような場合は、小規模個人再生、給与所得者再生いずれの対象にもなりません。債務総額が5,000万円を超えている場合は、通常の一般民事再生手続の対象となります。
個人再生を実行に移すためには、裁判所へ申し立てをして審査をパスしなくてはいけません。再生計画案の内容を裁判所が審査し、債権者の異議も出なければ認可決定が出ることになります。
再生計画案は、実際に実行可能なものでなければ裁判所に認められません。再生計画案の実行可能性は、主に家計収支表に照らして判断されることになります。
例えば、家計の余剰が5万円しかないのに、月額の返済が7万円の再生計画案を提出すれば、当然ですが実行可能性がないと判断されます。
また、個人再生では種類に応じて最低弁済額の基準が設けられています。再生計画案は、最低弁済額を上回る金額で作成されていなければなりません。
給与所得者再生の場合は、「債務総額を金額に応じて圧縮した後の額」「財産の総額」「可処分所得の2年分」の3つを比較して最も高い額が最低弁済額となります。
可処分所得については、給与明細や課税証明、源泉徴収票などをもとに一定の計算式で求められます。給与所得者再生の場合、可処分所得が最低弁済額となることが多く、返済額が高くなりがちです。
個人再生の申立てをした後も、裁判所の指示に適切に従わないと手続きを進めることができなくなってしまいます。
個人再生の申立書類が裁判所に届くと、裁判所ではまず書類に不備がないか確認します。不備があれば補正の可能性の有無によって、補正の可能性があれば補正の指示があります。
明らかに補正の可能性がなければ、申立て不適法ということで却下され、それ以降の手続きはされずに終わります。
補正不可能な不備とは、負債総額が5000万円を超えていたり、手続費用を期限までに納付しなかったり、債務者が個人ではなかったりなどの、そもそも個人再生の条件を満たしていない場合などです。
補正可能な不備とは、単純な誤記や記入漏れ、必要な種類が添付されていなかったりした場合などです。
個人再生の申立てをすると、一般的には1週間程度で裁判所から追完指示がきます。追完の期限は通常2週間とされていますので、その期間中に不備を修正して再提出してください。どうしても間に合わない場合は、期限の延長許可を求めることもできます。